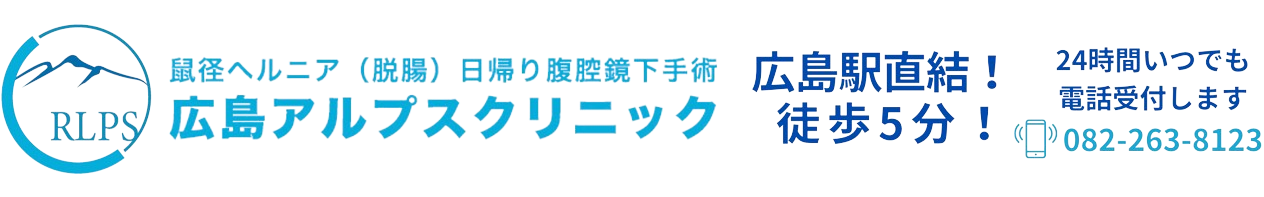鼠径ヘルニアは、多くの方が経験する一般的な疾患です。
日常生活に支障をきたす痛みを伴うことがありますが、なぜ痛みが生じるのでしょうか。
この記事では、鼠径ヘルニアの成り立ちから痛みが発生するメカニズムまで、わかりやすく解説していきます。
鼠径ヘルニアとは
鼠径ヘルニアは、おなかの中の臓器(主に腸管や腹膜)が、足の付け根(鼠径部)にある筋肉や腱の隙間から飛び出してくる状態です。この状態を「脱腸」と呼ぶこともあります。
私たちの腹部には、内臓を保護し支える複数の筋肉層があります。特に鼠径部には、精巣や血管が通る「鼠径管」という自然の通り道があり、この部分は比較的脆弱になっています。年齢とともに筋肉が弱くなったり、過度な腹圧がかかることで、この部分が広がってしまい、そこから腸が飛び出してくるのです。
特に男性は胎児期に精巣が腹腔から陰嚢へ降りてくる際に通った道(精索)があるため、女性に比べて鼠径ヘルニアになりやすい傾向があります。また、高齢者や喫煙者、慢性的な咳のある方、重い物を持ち上げる仕事をされている方なども、発症のリスクが高くなります。
鼠径ヘルニアとは
鼠径ヘルニアは、おなかの中の臓器(主に腸管や腹膜)が、足の付け根(鼠径部)にある筋肉や腱の隙間から飛び出してくる状態です。この状態を「脱腸」と呼ぶこともあります。
私たちの腹部には、内臓を保護し支える複数の筋肉層があります。特に鼠径部には、精巣や血管が通る「鼠径管」という自然の通り道があり、この部分は比較的脆弱になっています。年齢とともに筋肉が弱くなったり、過度な腹圧がかかることで、この部分が広がってしまい、そこから腸が飛び出してくるのです。
特に男性は胎児期に精巣が腹腔から陰嚢へ降りてくる際に通った道(精索)があるため、女性に比べて鼠径ヘルニアになりやすい傾向があります。また、高齢者や喫煙者、慢性的な咳のある方、重い物を持ち上げる仕事をされている方なども、発症のリスクが高くなります。
痛みが生じる原因
鼠径ヘルニアによる痛みには、いくつかの要因が関係しています。
それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
血流の変化による痛み
ヘルニアの袋の中に入り込んだ腸管は、その部分で血流が悪くなることがあります。
血流が減少すると、腸管の細胞に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり、痛みを感じる原因となります。
この状態が長く続くと、腸管がどんどん戻りにくくなり(嵌頓)、最終的には腸管が壊死してしまう可能性すらあります。
腹圧上昇による痛み
咳やくしゃみ、重い物を持ち上げるなど、おなかに力が入る動作をすると腹圧が上昇します。
腹圧が上がると、ヘルニアの部分により強い力がかかり、違和感や痛みを感じやすくなります。
特に立ち仕事が多い方や、力仕事をされる方は、この種の痛みを感じやすいことがあります。
組織の炎症反応による痛み
ヘルニアが起きている部分では、周囲の組織に炎症反応が起こることがあります。
炎症は体を守るための正常な反応ですが、その過程で痛みを感じることがあります。
また、炎症が続くと周囲の組織が硬くなり、さらなる不快感の原因となることもあります。
組織の圧迫と進展による痛み
腸管が飛び出すことで、周囲の神経や血管、筋肉などが圧迫されたり引き伸ばされたりします。
これらの組織には痛みを感じる神経が豊富にあるため、違和感や痛みとして感じられます。
特に歩行時や長時間の座位で症状が強くなることがあります。
嵌頓という状態について
鼠径ヘルニアの中でも特に注意が必要なのが「嵌頓」という状態です。
これは、飛び出た腸管が元の位置に戻れなくなってしまう深刻な状態を指します。
嵌頓が起こると、飛び出た腸管の血流が著しく悪くなり、強い痛みや吐き気、発熱などの症状が現れます。
この状態を放置すると、腸管が壊死(えし)→腹膜炎→敗血症、と致命的な経過を辿ります。
そのため、普段は自分で押し戻せていたヘルニアが戻らなくなった場合や、強い痛みが持続する場合は、すぐに医療機関を受診することが重要です。
まとめ
鼠径ヘルニアによる痛みは、血流の変化、腹圧上昇、炎症反応、組織の圧迫など、様々な要因が複雑に関係しあって生じます。
痛みの程度は人によって異なり、日常生活に支障をきたさない軽度なものから、緊急治療が必要な重度なものまでさまざまです。
早期発見・早期治療が重要で、特に日帰り手術の技術が進歩した現在では、比較的短時間で安全に治療を行うことができます。
気になる症状がある場合は、ためらわずに専門医に相談することをお勧めします。
また、予防の観点からも、適度な運動で腹筋を鍛えることや、過度な腹圧上昇を避けることが大切です。