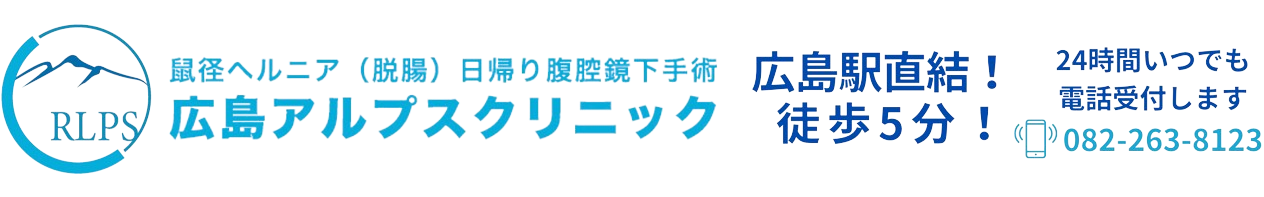鼠径部の「膨らみ」や「違和感」――。このような症状で悩む方は決して少なくありません。
その多くは鼠径ヘルニアによるものです。
今回は、鼠径ヘルニアの2つのタイプについて、その違いを詳しく解説します。
鼠径ヘルニアとは
私たちの体には、腹腔内の臓器を支える「腹壁」という強固な壁があります。
しかし、この壁に脆い部分ができると、そこから腸管や脂肪組織が飛び出してしまうことがあります。
これが鼠径ヘルニアです。
立ったときや力んだときに膨らみが現れ、横になると自然に戻る――。このような特徴的な症状が見られます。
鼠径ヘルニアのタイプ:内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニア
解剖学的な特徴――2つの「道」
人体の設計図において、鼠径部には2つの潜在的な弱点があります。
1つは「ヘッセルバッハ三角」と呼ばれる部分。ここから発生するのが内鼠径ヘルニアです。
腹筋の層が薄くなっている場所で、まるで壁の継ぎ目のような部分といえます。
もう1つは「内鼠径輪」。ここから発生するのが外鼠径ヘルニアです。
精巣に至る血管や神経が通る天然の「道」であり、この道が広がりすぎることで発症します。
それぞれの特徴――年齢が教えてくれるもの
内鼠径ヘルニアは、人生の歩みとともに現れます。40代以降、特に50代、60代に多く見られるのが特徴です。
長年の生活による「自然の摩耗」とも言えるでしょう。
重いものを持ち続けた仕事、慢性的な咳、便秘など、日々の暮らしの中での「積み重ね」が影響します。
一方、外鼠径ヘルニアは「生まれながらの特徴」が色濃く出ます。
赤ちゃんや小さな子供に多く見られ、若い成人でも発症することがあります。
先天的な要因が大きく、いわば体の設計図の中に、すでにその可能性が書き込まれているのです。
症状の特徴――タイプによる違い
内鼠径ヘルニアは、静かに始まります。最初は何となく違和感があるだけ。
しかし、徐々にその存在感を増していきます。
立ったとき、歩いているとき、特に重いものを持ち上げたときに、鼠径部の膨らみや痛みとして姿を現します。
外鼠径ヘルニアは、より明確に自己主張します。
特に子供の場合、泣いたときや力んだときに、はっきりとした膨らみとして現れます。
時には陰嚢にまで及ぶことも。大人の場合も、運動時や労作時に明確な形で気付かれることが多いのです。
診断のアプローチ――医師の目と技術
両タイプとも、熟練した医師の目と手による診察が基本となります。しかし、それぞれに特徴的な難しさがあります。
内鼠径ヘルニアは、時に「隠れん坊」のように見つけにくいことがあります。
特に体格の大きな方では、触診だけでは判断が難しい場合も。
そんな時、超音波検査やCT検査という「現代の目」が力を発揮します。
外鼠径ヘルニアは、比較的見つけやすいものです。しかし、小さな子供の診察では、また違った技術が必要となります。泣いている赤ちゃんの診察には、優しさと的確さの両立が求められます。
治療方法――タイプに応じた適切なアプローチ
内鼠径ヘルニアの治療は、現代医療の英知の結晶とも言えるメッシュ手術が標準です。
開放手術と腹腔鏡手術、どちらのアプローチも可能で、患者さんの状態に応じて最適な方法を選択します。
外鼠径ヘルニアは、年齢によって異なるアプローチを取ります。子供の場合は、シンプルかつ確実な高位結紮術が選ばれます。
一方、大人の場合は内鼠径ヘルニアと同様、メッシュによる修復術が基本となります。
まとめ
内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニア。発生の場所が違えば、その特徴も、最適な治療法も変わってきます。
しかし、どちらの場合も、早期発見・早期治療が望ましいという点は変わりません。
体の違和感に気付いたら、それはあなたの体からのメッセージかもしれません。
専門医による適切な診断と治療で、その不安を解決に導くことができます。